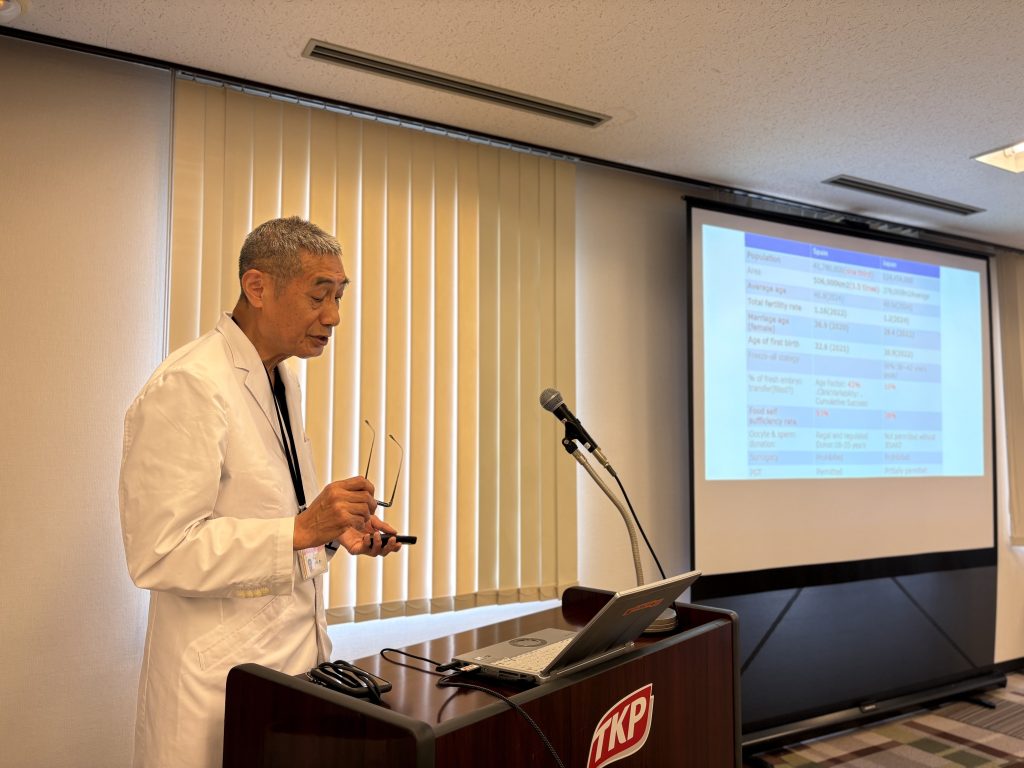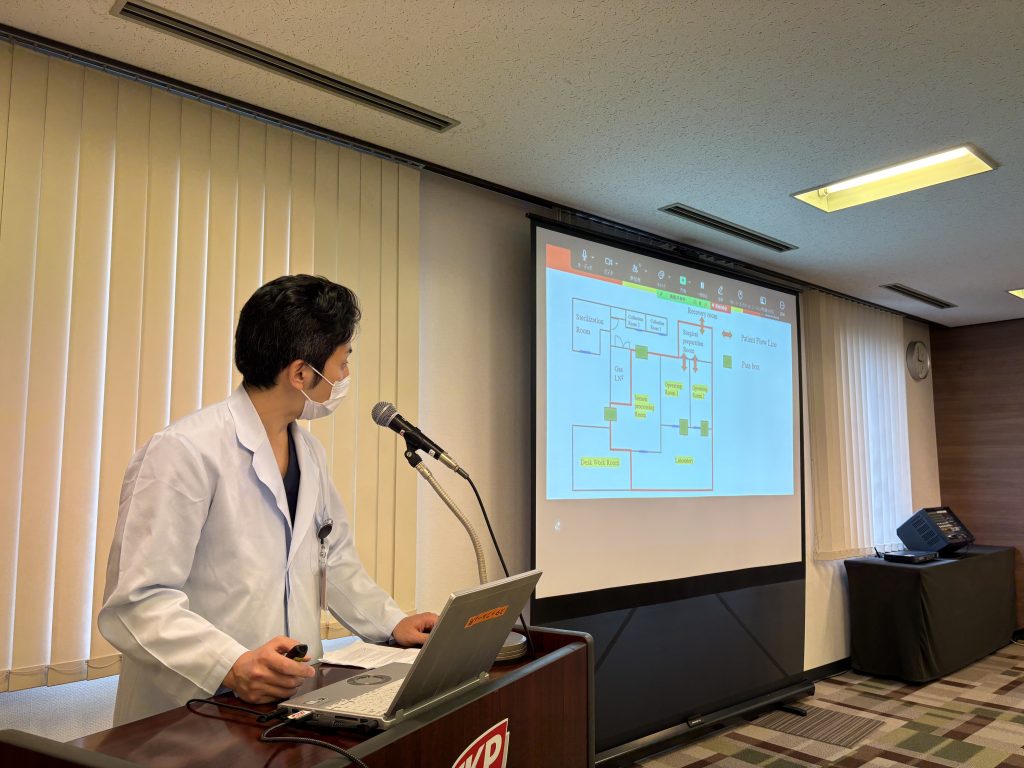医療コラム
コラム 2025.04.28
4月26日(土)スペイン医師団との交流会を開催しました

こんにちは、生殖医療相談士の越智です。
4月26日(土)に当院にスペインの医師団がお越しになり、交流会を開催いたしました。
当院では理事長の京野を筆頭に、毎年様々な学会に参加しています。
特に欧州生殖医療学会(ESHRE)とアメリカ生殖医学会(ASRM)には毎年のように参加しております。
こうした学会活動を通じて、世界の最先端の医療では何が行われているかという知見をお互いに共有することで、検査や治療はもちろんのこと、様々な診療システムなどの改善を図っています。
今回の交流において、様々な情報をお互いに発表を通じて共有し、様々な発見がありましたので、その一部を紹介させていただきます。
1.当院からの発表(理事長 京野廣一)
当院のデータならびに公表されている日本産科婦人科学会のデータを共有しながら、スペインとの比較や様々な日本の良い点や諸外国と比べた時の課題について発表いたしました。
特に日本では、やや過剰なまでに卵巣刺激後-採卵-受精の後にすべての受精卵を凍結する、「全胚凍結」ならびに凍結胚移植が主流となっています。
すべてが問題というわけではありませんが、この全胚凍結という方法はESHREのガイドラインにおいても、全症例に推奨されるものではなく、卵巣過剰刺激症候群のリスクが高いと考えられる際に推奨されるものと考えられています。
PGT(着床前胚染色体異数性検査)を行うような場合においては、全胚凍結が取り入れられますが、まだPGTの実施が全体としては認められていない日本において、この実態は世界から見たらやや異常なように見えるようです。
また、新鮮胚移植の方法の方が、周産期の合併症が少ないことも共通見解としてある中で、
凍結胚移植を否定するわけではないものの、新鮮胚移植がもっと取り入れられる方が本来自然なのではないか、などと様々な議論がかわされました。
2.スペイン医師からの発表
スペインの医師を代表して、GARCÍA TORÓN医師が発表くださいました。
とてもユーモアがあり、優しいドクターでした。
人口は日本に比べて半分以下、一方で国土面積はスペインの方が広大という比較の中で、非常に効率的に生殖医療を展開されている実態がわかりました。
得に、先述の新鮮胚移植については、全体の40%超で実施されており、凍結胚移植と比べて遜色のない妊娠率となっているとのこと。
また、この新鮮胚移植の多くは「胚盤胞」で行われているとのことです。日本での新鮮胚移植の多くは初期胚移植となりますので、こうした点にも違いが感じ取れます。
次に、スペインと言えば、卵子や精子を提供して行われる提供型の生殖医療(卵子提供・精子提供・胚提供)が世界的に見ても活発に行われていることで知られています。
1万人以上のお子様が年間で卵子提供を通じて出産されているということで、その件数の多さと、日本における社会通念とは大きく文化が異なることを肌で感じました。
(現在、日本では提供精子や提供卵子を用いた生殖医療については、今国会で特別法案が審議中となります)
また、スペインでの生殖医療における待ち時間は非常に短いことも教えていただきました。
最低限の採血や子宮鏡検査に留めることによって、滞在時間が30分程度になるようにしているとのことでした。
この点については、スタンダードなモデルがそれぞれ違うことから、良し悪しを判断するのは難しいことですが、日本における考え方と比べ、より効率的にという思考がとても強いように感じました。
3.当院培養部主任 奥山紀之からの発表
日本は、世界的に見ても、培養技術や凍結技術が高いことはもちろんですが、災害大国としても知られています。
当院の標準的な設備や技術面の紹介に加え、こうした災害対策についても詳細に紹介したところ、大変興味深く聞いてくださり、その後も活発な議論がかわされました。
このような交流会を通じて、常に新しい考え方、知識を身に着け、今不妊治療を受ける患者さんに対して最適な医療を提供できるように務めてまいりたいと思います。
診療時間
診療科目:婦人科・泌尿器科(生殖補助医療)
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30〜16:30 (最終予約 15:00) |
– |
- ※
- 日曜は 8:30~14:00(受付は12:00まで)で診療いたします
- ※
- 祝日も休まず診療いたします
- ※
- 診療内容によって予約可能時間が異なります。
不明点はスタッフまでお問い合わせください。
ご予約・お問い合わせ
03-6408-4124
| お電話 受付時間 |
|
|---|
- ※
- 祝日は曜日に順じます
- ※
- 当院ではお電話での待ち時間短縮と対応品質向上のため、自動音声による目的別案内システムを採用しています。