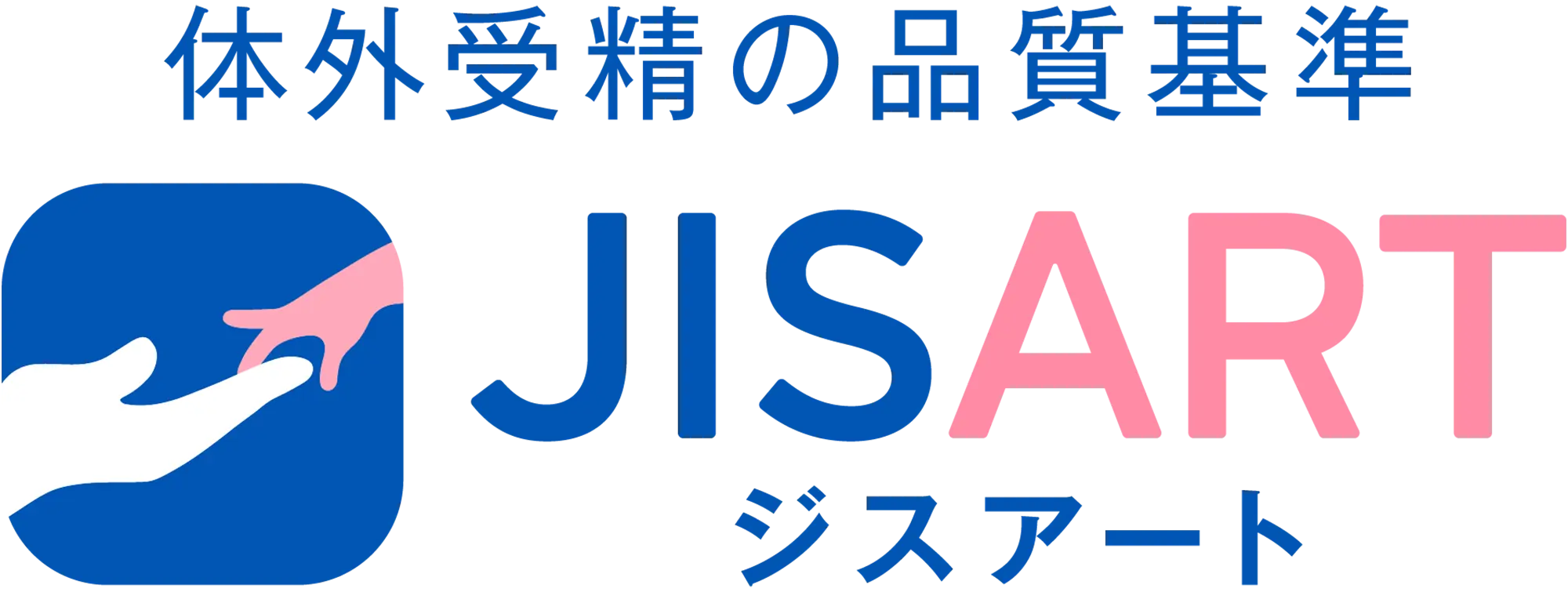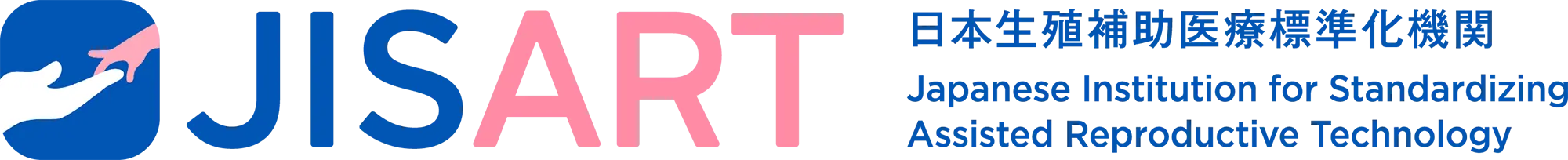不妊治療に関する費用補助や有効な制度について
2022年不妊治療の保険適用が開始され、2年が経過しました。
不妊治療の経済的な負担を軽減しようという大きな目的があり進められてきましたが、費用負担については、当然低いに越したことはないですし、その上で、本来の目的である妊娠・出産というゴールに向かって、どれだけ最短距離で歩んでいけるかが重要になります。
こうした費用負担の軽減と保険診療下での妊娠率の向上のために有効な制度として、先進医療、高額療養費制度、民間保険の活用がありますので紹介いたします。
先進医療とは
先進医療とは、不妊治療などの分野において、特定の医療技術や方法が新しく、今後のエビデンスの確立が期待される治療を指します。2022年から不妊治療は保険適用となり、多くの方が「先進医療」に触れる機会が増えました。
これまで不妊治療は自由診療が主流で、助成金によって治療費の負担が軽減されていましたが、保険適用となると自由診療との併用ができず、治療内容に制限が加わります。先進医療はその中で、特定の自由診療が保険適用治療と同時に行える例外的な内容です。
保険収載される治療はエビデンスが確立しているものが多く、自由診療はエビデンスが未確立の治療が中心です。先進医療には、今後エビデンスが確立することで保険収載が期待される治療方法が含まれています。
先進医療は、保険医療に移行する可能性が高い「先進医療A」と、Aよりも科学的証拠が乏しいとされる「先進医療B」に分類されています。
具体的な費用について言えば、体外受精を行う場合、先進医療の「タイムラプス」を利用することができます。この場合、タイムラプス以外の治療はすべて保険適用となり、患者さんの負担は3割となります。しかし、タイムラプスの費用は全額自己負担となり、例えばタイムラプスが3万円であれば、保険適用分に加えて3万円を支払うことになります。
さらに、生命保険の中には先進医療に関する補償が含まれている場合がありますので、ご自身の保険内容を確認してみることをお勧めします。また、自治体が先進医療に対して助成金を出していることもありますので、こうした制度についても今後情報をお届けできればと思います。
先進医療A
不妊治療の先進医療Aとして、現在登録されている治療は、
(受精や培養関連)
PICSI
IMSI
タイムラプス
(胚移植関連)
SEET法
二段階胚移植法
(子宮内環境の検査)
子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE)
子宮内フローラ検査
子宮内膜受容能検査(ERA)
子宮内膜受容期検査(ERPeak)
があります。
特に多くの医療機関で実施されているのがタイムラプスです。
タイムラプスは、培養器に内蔵されたカメラによって、胚培養中の胚を一定間隔で自動撮影し、培養器から取り出すことなく、正確な胚の評価が可能となる技術と説明されています。
スマートフォンのカメラなどでタイムラプスという機能を使用したことがあるという方もいらっしゃると思いますが、コマ送りのように連続的に撮影した写真で、画像の変化を確認することができます。
従来、受精卵の発育は培養士が培養器から都度取り出して、目視によって確認をしてきました。
培養器内の環境は厳密に管理されていて、一度その環境から出してしまうことは理論的には良くないことだと考えられていました。また、目視による確認となれば、当然人による誤差も出てしまう可能性があります。
これらの問題を一度に解消できると考えられているのがタイムラプス培養です。
大変な思いをしながら得た受精卵をより確率高く、良い受精卵に育てるための工夫ですね。
標準的に利用されている治療ではありますが、最近はさらにそこにAIが搭載されるなど年々進化しているようです。
タイムラプス関連のコラムは以下からも確認いただけます。
先進医療B
現在、先進医療Bとして登録されている治療はPGTとタクロリムスの利用です。
特に、近年PGTは多くの方が待ち望んでいる不妊治療の技術としてご存じの方も多いのではないでしょうか。
加齢と共に、受精卵の染色体の異常が増えてしまうことが広く知られていますが、
目視によって染色体の異常を確認することは今の技術ではできません。
そのため、受精卵の一部を採取して、専用の機会にて解析することで、その受精卵が染色体正常なのか異常なのかということを調べるのがこのPGTです。
染色体異常の受精卵を胚移植で体内に戻しても、妊娠することができないか、妊娠したとしても流産してしまいます。
そのためPGTには、妊娠率を高め、流産率を低くする、という効果が期待されていますが、現在は先進医療Bへ登録されています。
先進医療BはAよりも科学的証拠が乏しいとされる分類であるため、適用や実施可能な医療機関も限定的になります。
そのため、まだ日本全国でPGTが利用できるという状況ではありません。
PGTは主に、良い受精卵を体内に何度も戻しても妊娠に至らない方や繰り返して流産する方が適応となる治療法です。
日本は世界的に見ても、不妊治療を行う患者さんの年齢が高いことで知られているため、この治療ができるようになることで恩恵を受ける方も非常に多いと考えられています。
今後の動向が注目されます。
「高額療養費制度」
不妊治療の費用負担を下げるという目的から不妊治療の保険適用は進み、保険で受けられる治療内容についての患者さんのご負担は3割にまで低下しました。
実はさらに、自己負担額を低下させることができる制度があります。
それが「高額療養費制度」です。
高額療養費制度とは、保険適用の治療において1ヵ月の医療費が高額になったときに、本人の自己負担限度額を超えた額が公的医療保険(健保や国保)から払い戻される制度です。
利用方法としては、医療機関を受診した後にご自身で公的医療保険に申請して、払い戻しを受けるパターンと、工程器医療保険が発行している「限度額認定証」を提示することで、医療機関でのお支払いの際に負担額を軽減するという方法があります。
体外受精を実施した場合で考えると、限度額は「女性の年収」によって定義されており、以下の通りです。
また、高額療養費制度には、直近12ヵ月間に3回以上、高額療養費制度の対象になった場合、4回目からさらに自己負担限度額が軽減される「多数回該当」制度もあります。
多数回該当になると、更に負担額は軽減されますので、治療が長期にわたる方は必ず申請しましょう。
なお、高額療養費制度では、自費診療のみの治療や、保険診療と併用できる先進医療を対象としていないので注意が必要です。
民間保険
不妊治療の保険適用が広がる中で、人工授精(AIH)や体外受精(IVF)、顕微授精(ICSI)が「手術」に分類されることにより、民間の医療保険から給付金を受け取ることが可能になっています。これに従って、医療保険の利用が増えており、自費診療である先進医療に対応する保険商品も展開されています。
現在の医療保険市場では、一般の医療保険に不妊治療に関する保障(特約)が付加される形が主流です。これにより、病気や怪我のリスクに備えつつ、不妊治療に対する経済的支援を受けられる仕組みが整っています。
具体的な給付条件や給付回数の上限は保険会社によって異なるため、患者さまご自身で、加入前に確認することが重要です。多くの医療保険では、体外受精(IVF)や顕微授精(ICSI)の際に実施される採卵や胚移植に対する給付金が支給されます。一部の保険商品では、男性の不妊治療、たとえば清掃内精子回収術や男性不妊治療などの経費も給付対象となる場合があります。
ただし、不妊治療への保障が開始される時期には注意が必要です。多くの保険商品では、契約から一定の期間(例:2年)を経過しないと、不妊治療に対する給付が受けられないことが一般的です。このため、保険契約時には免責期間などの確認が不可欠です。こちらの条件も患者さまご自身で確認をお願いいたします。
給付金については、治療費の支払いが全て終了した後、保険会社に請求を行う必要があります。支払い手続きや必要書類についても確認しておくことで、スムーズに給付を受けられます。
不妊治療は心身ともにも大きな影響を及ぼすため、経済的な負担軽減策として医療保険の選択と活用は重要です。
診療時間
診療科目:婦人科・泌尿器科(生殖補助医療)
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30〜16:30 (最終予約 15:00) |
AM のみ |
- ※
- 火曜は 7:30~12:30(受付は11:00まで)で診療いたします
- ※
- 日曜は 8:30~14:00(受付は12:00まで)で診療いたします
- ※
- 祝日も休まず診療いたします
- ※
- 診療内容によって予約可能時間が異なります。
不明点はスタッフまでお問い合わせください。
ご予約・お問い合わせ
03-6408-4124
| お電話 受付時間 |
|
|---|
- ※
- 祝日は曜日に順じます
- ※
- 当院ではお電話での待ち時間短縮と対応品質向上のため、自動音声による目的別案内システムを採用しています。